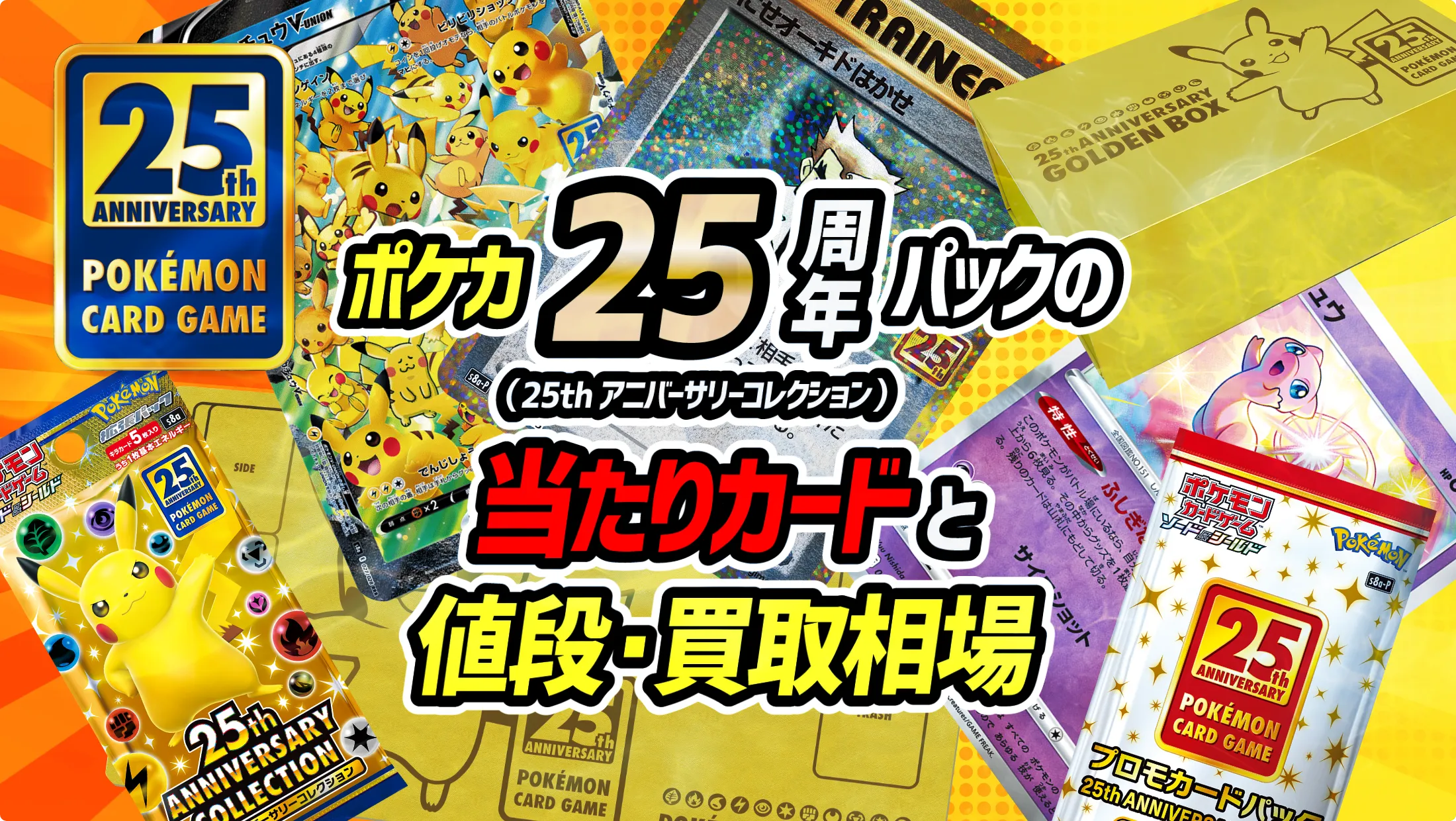ロストギラティナとはどんなデッキ?長所と短所を徹底解説
「ロストギラティナ」は「ロストギミック」の安定感とメインアタッカーである《ギラティナVSTAR》の高打点が特徴で、どんなデッキタイプに対しても勝ち筋があるため、初心者から上級者まで幅広く人気があります。
2024年の「Eマーク」のレギュレーション落ちでデッキのコンセプトが大きく変わりましたが、依然として強いデッキですので大会に参加する方は要チェックです!
序盤を「ロストギミック」の手札補充にあて、ロストゾーンにカードがたまった中盤以降には、大型のポケモンが相手なら《ギラティナVSTAR》、ベンチポケモンを取りたいなら《ヤミラミ》《かがやくゲッコウガ》と相手に合わせてアタッカーを選択し、《ミラージュゲート》で必要なエネルギーを一度に用意して攻めるという対応力の高い後半追い上げ型のデッキです。
《アクロマの実験》や《キュワワー》の特性「はなえらび」によって一部のカードをロストゾーンに送り使用できなくなってしまうため、ゲーム序盤の段階からゲーム終盤の展開を想定したプレイングが求められる、使用難易度がやや高いデッキでもあります。
前レギュレーションでは《頂への雪道》の強力な妨害性能が強みでしたが、Fレギュ環境では大型を取る仕事を《ギラティナVSTAR》に任せた「ロストバレット」といった形に落ち着きました。
「ロストギラティナ」の長所
「ロストギラティナ」の長所は大きく分けて5つあります。
- 「ロストギミック」の安定感と加速力
- 「アビスシーク」による最低保証
- 《ギラティナVSTAR》の高打点・高耐久
- サブアタッカーの対応力
1. 「ロストギミック」の安定感と加速力
「ロストギミック」は、《キュワワー》の特性「はなえらび」や強力なドローサポートである《アクロマの実験》の手札補充による、高い安定感が魅力のギミックです。
さらに、エネルギー加速として現行のスタンダードで最高クラスの性能を持つ《ミラージュゲート》を使用できるため、ロストゾーンさえたまればいつでもアタッカーを動かせる加速力も魅力です。
「ロストギラティナ」は、「ロスト系デッキ」のなかでメインアタッカーに《ギラティナVSTAR》を採用したものですが、安定感や加速力といった特徴はしっかり保持しています。
2. 「アビスシーク」による最低保証
-

画像提供:駿河屋
[s11] 080/100 (RR)
「ロストギラティナ」が、その他の「ロスト系デッキ」に勝る要素として《ギラティナV》の「アビスシーク」があります。
「ロスト系デッキ」の強力な要素である《ミラージュゲート》や《ヤミラミ》の「ロストマイン」はロストゾーンの枚数が使用の条件になっています。
そのため、すべての「ロスト系デッキ」の最序盤の目標は「ロストゾーンをためる」ことになります。
各ターンの目標とするロストゾーンの枚数は対戦するデッキによって異なりますが、先攻の場合は1ターン目に3枚、2ターン目に7枚、3ターン目に10枚、後攻の場合は1ターン目に4枚、2ターン目に7枚、3ターン目に10枚を目標とする場合が多いです。
これらは、ロストゾーン4枚で《ウッウ》の「ロストプロバイド」が、7枚で《ミラージュゲート》が、10枚で《ヤミラミ》の「ロストマイン」及び《ギラティナVSTAR》の「スターレクイエム」が使用可能になるからです。
《ギラティナV》が採用されていない「ロスト系デッキ」でロストゾーンをためることができるカードは、《キュワワー》が4枚、《アクロマの実験》が4枚、《ロストスイーパー》が1~4枚の合計9~12枚しかありませんので、《アクロマの実験》を引けていない場合、各ターンの目標枚数に到達できないことが多いです。
ところが「ロストギラティナ」では、《アクロマの実験》を引けていなくても《ギラティナV》の「アビスシーク」がありますので、ロストゾーンをためることができます。
「アビスシーク」を使う行為そのものは「強い」わけではありませんが、1ターンを犠牲にすることで次のターン以降の動きを理想に近いものにするという働きがあります。
《アクロマの実験》を引くという理想の行動ができなくても、《ギラティナV》の「アビスシーク」が最低限の動きを保証してくれるため、安定感が高いという点が「ロストギラティナ」ならでは長所です。
3. 《ギラティナVSTAR》の高打点・高耐久
「ロスト系デッキ」のアタッカーは、《ウッウ》《ヤミラミ》《かがやくゲッコウガ》と優秀なものが多いですが、いずれもポケモンVやポケモンexを相手取るには火力が低く、複数ターンかけダメージを蓄積させる必要があります。
そこで、活躍するのが「ロストインパクト」で280点もの高打点を出せる《ギラティナVSTAR》です。
よくデッキに採用されるポケモンのHPは以下の通りなので、280出るということは、ほとんどすべてのポケモンを一撃で気絶させることができるということです。
| カード種 | HP |
|---|---|
| ポケモンV | ~220 |
| ポケモンVSTAR | ~280 |
| ポケモンVMAX | ~330 |
| ポケモンex(たね) | ~230 |
| ポケモンex(進化) | ~340 |
ポケモンVMAXのPH330には少し足りませんがそれでも、大会で活躍することが多い《ミュウVMAX》や《レジエレキVMAX》のPH310には《こだわりベルト》を付ければちょうど310に届きますし、その他1度だけなら「スターレクイエム」で強制的に気絶させることもできます。
器用に立ち回れるが、大型ポケモンの前に足踏みさせられるという「ロスト系デッキ」の弱点を、《ギラティナVSTAR》で補うという構成をしているのが「ロストギラティナ」というデッキなのです。
また、《ギラティナVSTAR》はHP280とポケモンVSTARのなかで最上位のため、簡単には気絶させられない耐久力があります。
《キュワワー》《ウッウ》《ヤミラミ》など小型のポケモンが気絶させられて、サイド残り1枚になってから、《ギラティナVSTAR》をバトル場に立てることで、1ターン稼ぐという選択肢も取ることができます。
高耐久・高打点の《ギラティナVSTAR》が入ったことで幅広い戦い方ができるのが「ロストギラティナ」の長所です。
4. サブアタッカーの対応力
-

画像提供:駿河屋
[s11] 033/100 (U)
「ロスト系デッキ」には、アタッカーとして《ウッウ》《かがやくゲッコウガ》《ヤミラミ》と優秀なポケモンがそろっています。
《ウッウ》は特性の「ロストプロバイド」によりエネルギーなしで「おとぼけスピリット」が使えるため、エネルギーを《キュワワー》がにげるために使用してロストゾーンをためたい最序盤から攻勢に出ることができます。
打点も110と高く、ルールを持たないポケモンを1回で、ポケモンVやexでも2回で気絶させることができる優秀なアタッカーです。
特性の「かくしふだ」のみを目当てにデッキの潤滑油として採用されることもある《かがやくゲッコウガ》ですが、「ロスト系デッキ」では《ミラージュゲート》を使うことで「げっこうしゅりけん」によるベンチ狙撃を行えます。
先攻の2ターン目に、「げっこうしゅりけん」で相手のベンチに並んだ種ポケモンを2体処理できた場合、ほぼ勝敗は決したようなものです。
相手が《マナフィ》を置いてこなかった場合は、積極的に狙っていきましょう。
3体目のアタッカーは《ヤミラミ》です。
-

画像提供:駿河屋
[s9]031/100(U)
「げっこうしゅりけん」の対策にベンチに出された《マナフィ》を処理したり、他のアタッカーが倒し損ねてベンチに下がったポケモンにとどめを刺したりと、最も器用に働くアタッカーです。
上級者になると、ダメカンをわざと分散させることでサイドを取らず、《ツツジ》や《ナンジャモ》による被害を減らすといったプレイングもします。
下の動画は《ギラティナVSTAR》は採用していない「ロストバレット」というデッキですが、《ヤミラミ》の「ロストマイン」でサイド6枚を1ターンで取り切って勝利しています。
メインアタッカーを前面に押し出した戦法が相性の悪い相手にも、これらの技だけで戦うこともあります。
器用な技が多いだけに、技を使う順番やダメージの割り振り方など、少しのプレイの巧拙が勝敗に大きく影響するため、非常に使いがいがあります。
「ロストギラティナ」をはじめとした「ロスト系デッキ」はこうした点がカードゲーマーから好評で、「ロスト系デッキ」のみが使用可能の自主大会が開催されるほど高い人気を誇ります。
「ロストギラティナの短所
安定感と対応力が魅力の「ロストギラティナ」ですが、良いところばかりとはいきません。「ロストギラティナ」の短所は以下の3点といえるでしょう。
- 立ち上がりの遅さ
- 低耐久ポケモンの多さ
- 「ギラティナ」進化ラインの不安定さ
1. 立ち上がりの遅さ
安定感の高さに加えて、エネルギー不要のアタッカー、自由なエネルギー加速、ダメカンのばらまき、強制気絶など、強力なカードが多い「ロストギミック」ですが、ロストゾーンの枚数をためなければ能力を使えないという条件から、序盤をロストゾーンの枚数確保に充てねばならず、どうしても動き出しが遅いのが弱点です。
各ターンの目標とするロストゾーンの枚数を、先攻の場合は1ターン目に3枚、2ターン目に7枚、3ターン目に10枚、後攻の場合は1ターン目に4枚、2ターン目に7枚、3ターン目に10枚として、ここから1ターン遅れるだけなら巻き返すこともできますが、2ターン3ターンと遅れていくと追い上げは困難です。
・1ターン目に《キュワワー》を展開できる枚数
・《アクロマの実験》または《ギラティナV》へのアクセス率
・《ロストスイーパー》の採用
各ターンのロストゾーンの枚数目標は、先攻1ターン目以外は《アクロマの実験》を打つことが前提にあります。
例えば、先攻1ターン目の3枚は《キュワワー》の「はなえらび」×3回で、後攻1ターン目の4枚《キュワワー》の「はなえらび」×2回+《アクロマの実験》、後攻2ターン目の7枚は《キュワワー》の「はなえらび」×1回+《アクロマの実験》となっています。
《アクロマの実験》のかわりに《ギラティナV》の「アビスシーク」をするにしても、《キュワワー》の必要枚数は変わりません。
《キュワワー》《ギラティナV》を展開できる《バトルVIPパス》や《ネストボール》の枚数、《アクロマの実験》を探せる《ポケギア3.0》の採用枚数などしっかりと調整しておきましょう。
《キュワワー》《ギラティナV》《アクロマの実験》の3枚は、手札を増やしながらロストゾーンをためられるカードですが、これらに必要な枚数アクセスできなかった時、無理やりロストゾーンをためる手段として《ロストスイーパー》があります。
自分の場のスタジアムやポケモンのどうぐを対象に使うことでロストゾーン2枚増やすことができます。
手札を3枚も消費することになるので、テンポよく動くことがなによりも重要だと判断した場合の緊急手段ではありますが、サイドの取り合いでおいていかれないための選択肢の一つとして覚えておきましょう。
2. 低耐久ポケモンの多さ
「ロストギミック」のもう一つの弱点として、ポケモンのHPの低さがあります。以下の表の通り、全体的にHPが低いので、ほぼ毎ターンサイドを1枚は取られると思ってプレイした方がいいでしょう。
特に序盤に複数展開する《キュワワー》のHPが70と低く、《ミライドン》の「アクセルピーク」(テツノカシラex2枚)で倒されてしまうほか、《かがやくゲッコウガ》の「げっこうしゅりけん」など、打点が低い傾向にあるベンチ狙撃わざでも簡単に落とされてしまいます。
また、《ギラティナV》もHP220とポケモンVの標準的な値しかないため気絶させられやすく、《ギラティナVSTAR》に進化するまでのタイムラグを狙われてサイドを2枚取られる、というケースも多いです。
使用時はサイドを取られやすいデッキであることを前提とした立ち回りが求められます。
3. 「ギラティナ」進化ラインの不安定さ
《ギラティナVSTAR》の高火力・高耐久は「ロストギラティナ」の強みではありますが、V進化ポケモンであるというのは弱点でもあります。
具体的には、《ギラティナV》と《ギラティナVSTAR》両方を引き込まなければアタッカーとして成立しない点、《ギラティナVSTAR》のサーチが難しい点、進化させるために1ターンのタイムラグがあるため速効性に欠ける点、進化前の《ギラティナV》を狙われてサイドを取られやすい点、《ギラティナV》《ギラティナVSTAR》の複数採用でデッキを圧迫する点などがあります。
これらは、サイドを2枚以上取られるポケモンを採用していない「ロストカイオーガ」や非進化のアタッカーである《カイリューV》や《ライコウV》を採用した「ロストバレット」にはないデメリットですので、前述のメリットと比較して十分に検討しましょう。
「ロストギラティナ」のデッキ構成と大会入賞・優勝レシピ
「ロストギラティナ」の大会入賞・優勝レシピ

戦績:ジムバトル優勝
開催日:2024年3月10日
【デッキコード】FFfFkb-tjrzgx-FFFwk5

戦績:ジムバトル優勝
開催日:2024年3月10日
【デッキコード】wvVFfk-JHqhqX-ffF5kF

戦績:ジムバトル優勝
開催日:2024年3月10日
【デッキコード】p33Xy2-NuAGK6-2MySyp
「ロストギラティナ」の回し方
デッキ内容が把握できたところで、実際の動き方を確認してみましょう。
ポケモンカードは、《バトルVIPパス》や《ネストボール》のように任意のポケモンをデッキから探すカード(サーチ系カード)が豊富にあるため、展開の再現性が非常に高いです。
強い展開を毎回再現するためには、まず自分のデッキの「理想の動き」を把握していなければなりません。
最終的な勝ち方を前提として、「ロストギラティナ」における「理想の動き」を、先攻・後攻とターンごとに分けて解説します。
「ロストギラティナ」の勝ち方
「ロストギラティナ」は対応力が高く様々な戦法を取ることができるデッキですが、最も強力なのは、《ギラティナVSTAR》を前面に押し出し相手の大型ポケモンを倒して一気にサイドを取り進める戦い方です。
デッキを使い始めたばかりの方は、まずはこの戦い方を安定して再現できるようにしましょう。
この戦い方では、《ギラティナVSTAR》がどれだけ早く「ロストインパクト」を使えるかで勝敗が変わります。
《ギラティナVSTAR》が最速で「ロストインパクト」を使えるのは、2ターン目に《ギラティナV》を進化させ《ミラージュゲート》+手札から1枚エネルギーを付けるパターンです。
このパターンを実現するためには《ミラージュゲート》の使用条件である「ロストゾーン7枚以上」をクリアする必要があります。
これを前提として、各ターンの理想の動きが決まっていきます。
各ターンの目標とするロストゾーンの枚数は、先攻の場合は1ターン目に3枚、2ターン目に7枚、3ターン目に10枚、後攻の場合は1ターン目に4枚、2ターン目に7枚、3ターン目に10枚を目標とする場合が多いです。
1ターン目
先攻

「ロストギラティナ」の最序盤の目標は「ロストゾーンをためる」ことです。
先攻ならば1ターン目に3枚ロストゾーンをためておけば、2ターン目に無理なく7枚以上ためることができます。
先攻1ターン目に、損をせずにロストゾーンをためる手段は《キュワワー》の「はなえらび」しかありませんので、《キュワワー》は3体並べます。
加えて次のターンに《ギラティナVSTAR》に進化させるために、《ギラティナV》も1体用意する必要があります。
ベンチが残り2枠あるので2体目の《ギラティナV》や《かがやくゲッコウガ》を出したいかもしれませんが、どちらか1つにとどめておきましょう。
相手がベンチ狙撃を備えたデッキの場合、《マナフィ》を出さなければなりませんし、2ターン目に《ミラージュゲート》が打てなかったり《ギラティナVSTAR》に進化させられなかったりした場合、ベンチが埋まっていると《ウッウ》を出して攻撃することができなくなるためです。
後攻

後攻ならばロストゾーン4枚が目標となります。
後攻はサポートが使えますので、《アクロマの実験》で2枚ためることができます。
そのため場に出す《キュワワー》の枚数も2枚で十分になります。
逆に《ギラティナV》は先攻2ターン目に倒される恐れがあるので2体目を用意していきたいです。
また、相手がベンチ狙撃を備えたデッキの場合には《マナフィ》も出しておきましょう。
そして、このターンから技を使うこともできますので、ロストゾーンが4枚ためられており必要ならば《ウッウ》を出して「おとぼけスピリット」、ためられていないならば《ギラティナV》で「アビスシーク」をします。
2ターン目
先攻でも後攻でも、2ターン目からは攻撃に出られるターンです。
《ギラティナVSTAR》の用意ができているならば「ロストインパクト」を使ってもいいですし、相手のベンチに小型のポケモンが多いなら《かがやくゲッコウガ》の「げっこうしゅりけん」で複数処理してしまうのも良いでしょう。
ただし、「ロストギラティナ」は2ターン目に攻撃できずとも十分に巻き返しができるデッキです。
無理をして《ミラージュゲート》から動かなくとも、《ナンジャモ》や《ジャッジマン》での手札干渉や《頂への雪道》の設置などで妨害しながら《ウッウ》の「おとぼけスピリット」でHPを110削っておくだけでも十分に強力です。
また、1ターン目に思うように動けなかった場合は、引き続きロストゾーンをためるために動きましょう。
返しのターンに気絶させられる可能性が高いので苦しい動きでは在りますが、このターンに《ギラティナV》で「アビスシーク」をすることもあります。
その他、返しのターンに《ギラティナVSTAR》が気絶させられることも考慮して、ベンチに2体目の《ギラティナV》を展開することもあります。
3ターン目以降
3ターン目以降は、展開によってアタッカーを使い分けていきましょう。
大型ポケモンを倒したいなら引き続き、《ギラティナVSTAR》で戦います。
このターンからは《ヤミラミ》の「ロストマイン」の起動が見えてきますので、次のターン以降に《ウッウ》《ヤミラミ》《かがやくゲッコウガ》で出せるダメージも考慮しながらダメカンを割り振っておきましょう。
初心者でも「ロストギラティナ」で勝ちきるには
サイド落ちを確認する重要性と優先順位
「ロストギラティナ」はゲーム開始時にサイドに行ってしまった(サイド落ちした)カードを確認するのが非常に重要なデッキです。
理由は「サイドを取るペースが遅いこと」「一部のカードをロストゾーンに送らなければならない」の2つです。
例えば、1ターン目に《キュワワー》の「はなえらび」で《ギラティナVSTAR》と《アクロマの実験》が見えたとき、通常なら《アクロマの実験》を手札に加えるでしょう。
実際、《ギラティナVSTAR》はゲーム中に使用する枚数が多くても2枚なので、3枚採用しているデッキならば1枚はロストゾーンに送る余裕があります。
しかし、《ギラティナVSTAR》が2枚サイド落ちしていた場合はどうでしょう。
「ロストギラティナ」は後半に追い上げるタイプのデッキなので、サイド落ちしたカードはゲーム終盤まで手札に加えることができません。
この状況で《ギラティナVSTAR》をロストゾーンに送ると、そのゲーム中は《ギラティナVSTAR》なしで戦うことになります。
大きな勝ち筋を失うわけにはいきませんので、この場合は《ギラティナVSTAR》を手札に加えるのが無難です。
このように、カードをロストゾーンに送る際の判断に大きく影響するため「ロストギラティナ」使う際は、しっかりとサイド落ちを確認しなければならないのです。
サイド落ちの確認というのは時間をかけてデッキをチェックすれば誰でも行うことができますが、大会では1ゲーム25分間しかありませんので、できる限り素早く確認する必要があります。
全てを確認していては効率が悪いので、優先度を付けて、重要なものだけを確認している方が多いです。
最初は以下の順番でサイドチェックをしてみることをおすすめします。
- 各種基本エネルギーの枚数
- 各種ポケモンの枚数
- 《ミラージュゲート》の枚数
- 《すごいつりざお》の枚数
- サポートおよび1枚採用のカード
最低でも1~3番は必ず確認しましょう。これらを確認しないと、そのゲーム中に技を使えるポケモンがはっきりしないので、ゲームプランを立てることができません。
特にエネルギーはロストに送ることが多いカード種です。しかし、送りすぎると終盤に技を使えなくて負けてしまいますので、できるだけゲームの序盤に確認して何を何枚まで送れるのかを把握しておきましょう。
カードを使う順番
「ロストギラティナ」を使い始めた方の多くが抱く疑問が「《アクロマの実験》と《キュワワー》はどっちから使うのが正解か?」というものです。
たまに例外もあるのですが、基本的には《アクロマの実験》から使った方が良いです。
この2枚に限った話ではありませんが、「選択肢が少ないものは、判断材料が多い状態で使う」というのを意識しておきましょう。
《キュワワー》の「はなえらび」は2枚から1枚を選ばばければならないので、「どちらをロストゾーンしていいかわからない」という状況になることがあります。
例えば、ロストゾーンが5枚の状態で《キュワワー》の「はなえらび」から《基本水エネルギー》と《基本超エネルギー》が見えたとき、どちらを選んでも大きく変わらないような気がします。
仮にら《基本水エネルギー》をロストした後に《アクロマの実験》を使い、《かがやくゲッコウガ》《ミラージュゲート》《いれかえカート》が見えたとします。
この場合はら《基本水エネルギー》を手札に加えておけば、《ミラージュゲート》と合わせてこのターンに《かがやくゲッコウガ》で「げっこうしゅりけん」を使うことができるので、それが正解です。
しかし、《アクロマの実験》で見えた中に《ヤミラミ》《ロストスイーパー》《頂への雪道》があった場合は、ロストゾーンを10枚ためて《ヤミラミ》で「ロストマイン」を使えますので、《基本超エネルギー》を手札に加えるのが正解です。
どちらの可能性もある状態では、「はなえらび」で正解を判断することができないのです。
「はなえらび」で「どちらをロストゾーンしていいかわからない」という状況にならないためには、できるだけ判断材料となる手札やロストゾーンを増やしておくことが重要です。
そのため、先に《アクロマの実験》を使う方が良いのです。
デッキ相性 - まずは有利な相手に勝ちを逃さない
「ロストギラティナ」は安定感と対応力があるため、どのデッキタイプを相手にしても勝ち筋があるのですが、不利なデッキが全くないというわけではありません。
デッキを使い始めたばかりだと相性差を覆すのは難しいので、まずは有利なデッキを相手にしたときにしっかり勝ちきることを意識しましょう。
大会で活躍しているデッキと「ロストギラティナ」の大まかな相性は表の通りです。
デッキを使いこなすためには、まずデッキの勝ちパターンを把握することが重要ですが、「ルギア系デッキ」や「連撃ウーラオス」を相手にするとなかなかやりたいことをさせてももらえません。
練習相手を選べるならば《ギラティナVSTAR》で勝つパターンの相手として、まず「アルセウスギラティナ」などの「アルセウス系デッキ」と対戦するのが良いでしょう。
その他、サイドアタッカーをうまく使って勝つパターンの相手として「パオジアンex」もよい練習相手となってくれます。
「サーナイトex」については有利ではありますが、お互いの状況に合わせて細かいプレイングが要求されますので、慣れないうちは負けてしまうこともあるかもしれません。
どういう瞬間に相手が苦しそうにしていたのかを確認して、プレイングを磨いていきましょう。


あわせて読みたい
著者情報
コメント
コメント0件
レビューはありません。